大政奉還、そして江戸城の無血開城。
幕末ドラマで必ず名が挙がる江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜は、幕府を滅ぼした無能か?新時代のきっかけを作った有能か?の議論が分かれる人物でもあります。
そんな慶喜の明治以降の暮らしは知らない人もいることと思います。
将軍を引退後の慶喜の暮らしは、誰もがうらやましいと思うほど充実した生活で歴代将軍の中でも長生きしました。
中央権力から距離を置き、「よく食べ・よく遊び・よく学ぶ」生活者として生きた晩年は、日本の近代的ライフスタイルの先取りそのもの。
ここでは、将軍職退任後の慶喜を中心に、静かで豊かな日々をたどってみます。
静岡で始まった謹慎と趣味の時間
戊辰戦争の最中、慶喜は静岡へ移り謹慎。
政治から身を引き、まずは心身を休めることに専念します。
この時期、油絵を学んだという記録が残っており、現在でも慶喜が描いた油絵が残っています。また、徳川宗家の家督は若い家達へ引き継がれ、慶喜自身は「徳川家の代表者」という役目からもふわりと離脱。旧代官屋敷で家族と穏やかな日常を過ごしました。
趣味の幅がすごい:写真・油絵・自転車・芸事
慶喜の後半生は、好奇心の塊。
狩猟や釣り、囲碁・謡曲・刺繍といった和の教養に加え、当時最先端の写真と油絵に夢中になります。自らカメラを構え風景や暮らしを撮影し、絵では西洋風の風景画を描く。
新奇なものを恐れず受け入れる柔軟さは、元将軍の堅さとは無縁です。さらに自転車にも乗り、現在でいうところのサイクリングも楽しんだと伝えられています。
幼少から磨いた武芸の延長で、手裏剣の腕前を語る逸話まで残るほど。刀、筆、レンズ、自転車の四つの道具を自在に操る「悠々自適な老後」が見えてきます。
食のこだわり:あだ名は「豚一様」
グルメでも有名だったのが慶喜。
慶喜の豚肉好きは有名で、ついたあだ名が「豚一様(ぶたいちさま)」。また、当時では珍しいパンや牛乳といった新しい食文化にも積極的に取り入れています。割と保守的な武家のトップだった人が、食においても新進的でした。
東京へ――銀座散歩と自家製アイスのある暮らし
時が過ぎ、慶喜も文明開化の最先端の東京へ拠点を移します。
最新のモノと人が渦巻く都会で、慶喜のミーハー心はさらに加速。銀座での買い物を楽しみ、家庭ではアイス製造器を手に入れ手作りアイスを食す。技術の新しさも味わいの新しさも、素直に楽しみます。晩年は小石川に居を定め、悠々自適の時間を満喫しました。
社交と距離感――旧臣とも新知識人とも
権力からは距離を置きつつも元将軍と言うだけあって、交友関係は旧幕臣や各界の人物と趣味や文化を媒体に良い関係を築きます。写真や絵は、話題と距離感をつくる便利なツールでもありました。
統治する/される関係を離れ、共通の好きなことを語り合いさまざまな人と交流していきましたあ。
名君か暗君か評価が分かれる徳川慶喜
明治以降、悠々自適な生活を送っていた慶喜も1913年に77歳で逝去。
葬儀には皇族・旧幕臣・外交官など数千人規模が参列し、東京の街では自然と歌舞音曲を控えたと言います。
慶喜の評価は今も分かれます。
もし、徹底抗戦を選んでいたのなら、江戸の都市機能や人的被害は計り知れなかったでしょう。そういったことを考えると、江戸城無血開城は江戸の人命を守った名君とも言えるでしょう。
そして、結果論ですが、慶喜は刀を掲げる代わりに退く勇気で日本の近代化を間接的に推進し、次の時代へ橋を架けたと整理してよいでしょう。
政治の座を降りたあと、暮らしと趣味に没頭し、新しい技術や文化をまっすぐ受け入れる柔らかさ。要所では、人命と都市を守るために引く判断ができる胆力。
徳川慶喜は勝つことでなく壊さないことを選び、その後は楽しむことで時代に追いつくことを選びました。最後の将軍の物語は、「よい引き際」と「しなやかな余生」の見本として、これからも語り継がれていくはずです。
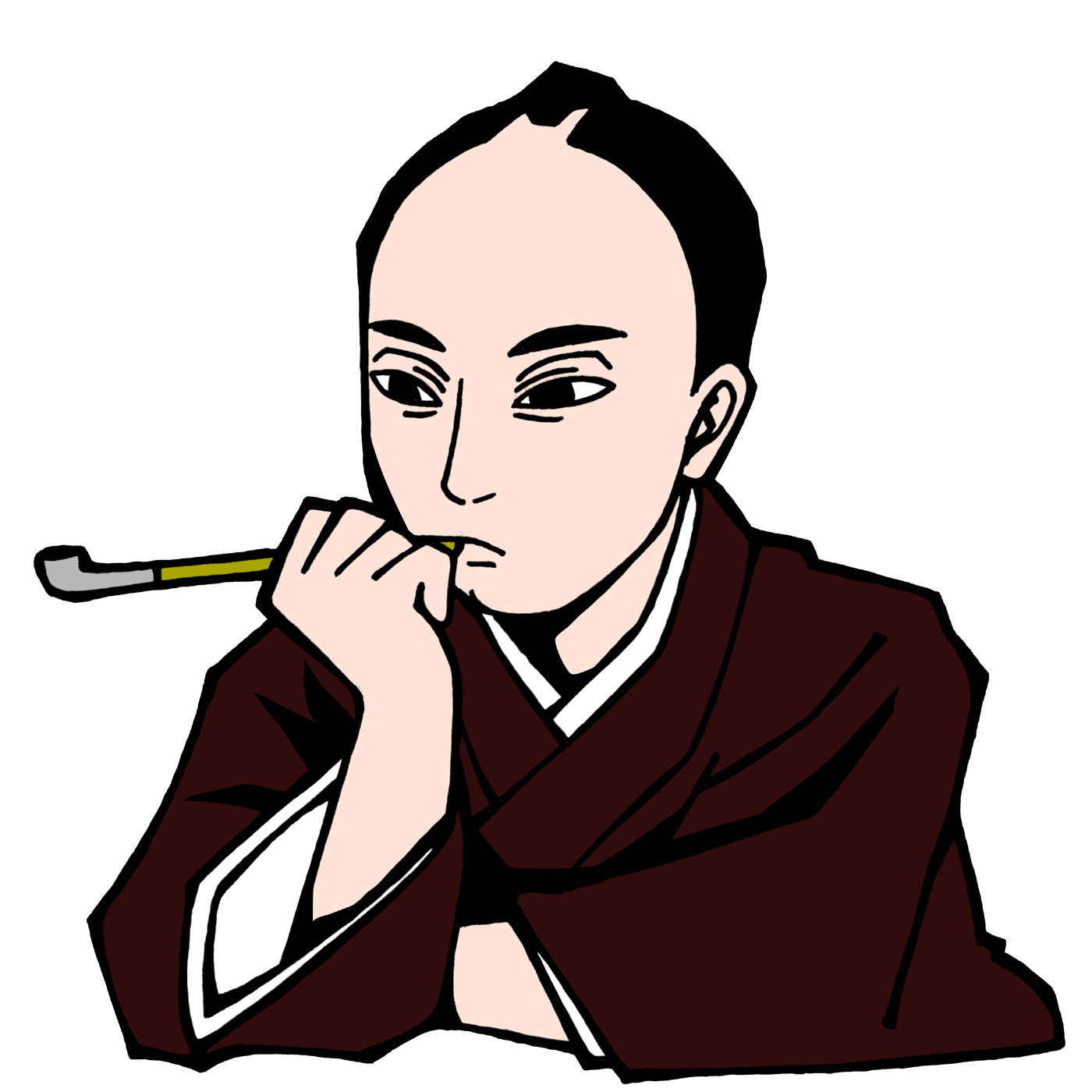


コメント