結城秀康(ゆうきひでやす)は徳川家康の次男として生まれました。
母は正室・築山殿に仕える侍女であったため、周囲から祝福されることはなく、築山殿は激しく怒ったと伝わります。父・家康も立場を考えてか、幼い秀康と積極的に関わることはなく、初めて対面できたのは3歳の頃、兄・松平信康の計らいによってでした。
1580年、信康が切腹、築山殿も処刑されると、次男である秀康が後継者に指名されるのではという見方もありました。しかし家康は、生後間もない三男・秀忠を優遇。秀康は後継者として扱われるどころか、小牧・長久手の戦いの和睦条件として豊臣秀吉のもとへ送られ、人質同然の立場に置かれます。
豊臣政権下での養子生活と武功
秀康はやがて秀吉の養子となり、「羽柴秀康」と名乗ります。秀吉は家康を上洛させるための交渉材料として秀康を利用しようとしたとされますが家康は応じず、親子の距離はさらに広がっていきました。
しかし秀康は豊臣家の一員として九州平定や小田原征伐に参陣し、武勇を示します。豊臣姓を名乗ることも許されるなど厚遇を受けますが、秀吉の側室・茶々が鶴松を出産すると状況は一変し、結城晴朝の養子となる事が決まりました。
結城家継承から越前68万石へ
結城家を継いだ秀康は一大名として独立します。
同年、家康の関東移封が行われると、結城領は徳川領の一部に組み込まれることとなりました。これを機に父子関係は改善し、朝鮮出兵では名護屋城で家康と行動を共にします。
関ヶ原の戦いでは、上杉景勝の南下を防ぐ重要任務を任されました。
本戦への参戦を望んでいた秀康でしたが、家康は江戸防衛を重視し、あえて後方任務を与えたのです。結果的に上杉軍を牽制し続けた秀康の功績は大きく、戦後には越前68万石を与えられ、松平姓を名乗る親藩大名となりました。家康にとって越前は、加賀の前田家や豊臣家を牽制する戦略的拠点でもありました。
将軍になれなかった理由と最期
家康の後継者は三男・秀忠に決定します。武勇に優れた秀康を推す声もありましたが、家康は重臣・大久保忠隣の「天下を治めるには文徳が大事」という意見に同調し、謙虚さと孝心を備えた秀忠を選びました。もし幼少期から家康に帝王学を学んでいれば二代目将軍・徳川秀康だったかもしれません。
秀康はその後も越前藩主として藩政に尽力しますが、1607年、わずか34歳で病死。同年、秀忠の弟・松平忠吉も亡くなったため、権力闘争による暗殺説もささやかれました。しかし当時の記録や秀忠による遺族への厚遇から、病死説が有力です。
もし秀康が将軍になっていたら
結城秀康は徳川家康と豊臣秀吉という二大権力者の間で複雑な立場を生き抜きました。大阪の陣まで豊臣・徳川の間で大きな戦争が起こらなかったのは、秀康の存在が一定の緩衝材になっていたとも考えられます。実際に徳川と豊臣がごたごたし始めたのは秀康の死後であり、もし存命なら歴史の展開は違っていたかもしれません。
結城秀康の治めていた越前国では「町の良きお殿様」として慕われた秀康。将軍にはならなかったものの、その存在感は徳川政権初期の安定に欠かせないものでした。

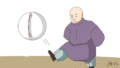

コメント