戦国時代の四国では統一の覇権をめぐり中小の領主たちがしのぎを削っていました。
その中で、土佐の弱小領主から身を起こし、四国全土を制覇した男がいました。
その名は、長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)。
「姫若子(ひめわこ)」と呼ばれた気弱な少年は、やがて“鬼若子”と恐れられる猛将へと成長し、四国を統一する偉業を成し遂げます。
しかし、その栄光の裏には数々の苦難がありました。
今回は長宗我部元親の生涯をたどりながら、四国統一の経緯を辿ってみたいと思います。
長宗我部家の再興と“姫若子”の登場
長宗我部元親は1539年、土佐の戦国大名・長宗我部国親の嫡男として生まれました。
当時の長宗我部家は、一時は本山氏に攻め込まれて滅亡寸前となったものの、国親の手腕によって辛うじて再興されていた状況。そんな中、誕生した元親は幼い頃からおっとりとした性格で知られ、「姫若子(ひめわこ)」とからかわれていたほど。家臣たちの中には、「こんな弱そうな若殿で大丈夫か」と不安視する声もあったといいます。
しかし、元親はその家臣たちの不安をよい意味で裏切る形で戦国屈指の猛将へと成長していくのです。
初陣での快進撃──鬼若子へと化ける
長宗我部元親の初陣は22歳のとき。
父・国親の命を受けて出陣し、敵方の本山氏を相手に大勝利を収めます。
この戦いを皮切りに、元親は戦場での才覚を次々と発揮。父の死後、家督を継いだ元親は本格的に土佐統一へと乗り出します。
元親が組織したのが農民兵による即応部隊「一領具足(いちりょうぐそく)」です。普段は農民として生活し、戦となれば武装して出陣するこの仕組みにより、限られた人口でも高い戦闘力を維持できました。
1570年代には宿敵・本山氏を滅ぼし、土佐を完全に掌握。さらに勢いに乗った元親は、隣国の阿波・讃岐・伊予へと侵攻を開始します。
四国制覇目前──信長の死がもたらした転機
四国各地で次々と敵を破り、元親の勢力は急拡大。1577年には阿波、1580年には讃岐を制圧し、ついに伊予にも進出。四国全土の統一が目前に迫る中、時代は大きく動き出します。
長宗我部元親は織田信長と外交関係を築き、長宗我部家の四国統一は黙認されていましたが、信長の急な方針転換で関係が悪化。信長は「土佐一国以外は明け渡せ」と元親に要求し、従わなければ討伐も辞さぬ姿勢を見せます。
こうして織田家では、三男・信孝と重臣・丹羽長秀が編成されました。着々と準備が進む中、1582年6月2日――突如として本能寺の変が勃発。信長が明智光秀に討たれたことで、四国攻めは中止されます。
元親にとっては千載一遇の好機でした。
豊臣秀吉との衝突──栄光から転落へ
信長が討たれたことで織田との衝突を避けられた元親ですが、次に政権を握った豊臣秀吉と対峙することに。秀吉は信長とは違い、「戦わずして服属させる」スタイルで戦国大名たちを取り込んでいましたが、四国を統一を果たした元親に警戒心を抱いていました。
1584年、小牧・長久手の戦いで徳川家康と対峙する一方、秀吉は四国方面への圧力を強めていきます
そして1585年、四国攻めがついに実行されました。
秀吉軍は10万以上の大軍を動員。対する元親は、四国全土でわずか4万の兵力をもって抗戦しましたが、多勢に無勢。あえなく敗北し、元親は土佐一国のみの安堵を条件に降伏を余儀なくされました。
これにより、長宗我部政権による四国統一はわずか数年で終焉を迎えるのです。
戸次川の戦いと、嫡男・信親の死
豊臣政権下では、腐らず九州討伐にも従軍します。
しかし1587年の戸次川の戦いで、最大の悲劇が襲います。
元親の嫡男・長宗我部信親が討死したのです。
この信親は聡明で、元親も深く信頼していた後継者。信親の死によって元親は深く落ち込み、以後、家中では跡継ぎ問題で混乱をきたすようになります。
長宗我部家の終焉──盛親と関ヶ原
元親は1599年に世を去り、家督は四男の長宗我部盛親が継ぎました。
しかし、時代はすでに徳川家康の天下。
1600年の関ヶ原の戦いで盛親は西軍に加担し、敗戦。
結果、長宗我部家は改易され、土佐から姿を消します。
土佐統一、四国制覇、そして一族の滅亡まで。
そのすべてが、わずか数十年のうちに起きた出来事でした。
長宗我部元親の生涯は、戦国という時代を象徴するような下剋上の物語。
気弱な若殿から、恐れられる名将へ。
土佐から四国全土へ。
そして中央政権との激突による失脚。
その一歩一歩は、血と汗と知略に彩られたものでした。
いまなお高知県をはじめとした四国各地では、長宗我部元親を顕彰する碑や祭りが残されており、地域の英雄として語り継がれています。

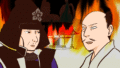

コメント