戦国時代には「戦に弱い」「判断を誤った」などの理由で主家を滅ぼし、後世において「無能」と揶揄される戦国武将たちがいます。
その代表例として挙げられるのが、今川氏真・大内義隆・朝倉義景の三人。時には「戦国三大無能大名」とまで呼ばれます。しかし、彼らの政治や文化面の業績に目を向けると、単なる「無能」という評価では到底収まりません。
今回はその中から、周防・長門を治めた大内義隆の生涯と山口文化について紹介します。
若き日の義隆は「無能」どころか有能な戦国大名だった
義隆が家督を継いだのは大永8年(1528)、22歳の時でした。
父・大内義興は将軍・足利義稙を京に再び迎え入れた実力者で、その功績から将軍より「義」の一字を賜るほどの人物。その血を継いだ義隆も、家督相続後は北九州や安芸へ積極的に出兵し、安芸守護・武田氏を滅ぼすなど領土を拡大しました。
将軍・足利義晴から幕政参加を求められるほど中央からも高く評価されていましたが、義隆はこれを辞退。理由は「領国経営を優先すべき」というもので、戦乱の時代にあっても内政や文化、外交の安定を重んじる姿勢が見て取れます。
転機となった出雲遠征の敗北
天文9年(1540)、義隆は出雲の尼子氏を攻めるべく月山富田城へ遠征します。しかし籠城戦に手間取り、尼子晴久の反撃で大敗。この敗戦を機に、義隆は軍事から距離を置くようになりました。
この転換は「戦う気を失った」とも批判されますが、逆にいえば彼は広大な領地を維持するため、戦争よりも平和的な発展に軸足を移したとも考えられます。
「西の京都」として発展した文化都市【山口】
周防山口は九州と本州を結ぶ交通の要衝。加えて、対馬経由で李氏朝鮮や明との貿易も盛んでした。義隆はこの地の利を活かし、山口を政治・経済・文化の中心地として整備していきます。
町割りは京の街を模し、寺院や庭園、学問所を整備。京や堺から学者・僧侶・詩人・芸術家が集まり、山口は「西の京」と呼ばれるまでに発展します。これらの都市計画や文化振興は、義隆の高い教養と安定した政治基盤があってこそ可能だったと言えるでしょう。
ザビエルが選んだ文化都市
義隆の文化政策が国際的にも評価された出来事があります。天文18年(1549)、フランシスコ・ザビエルが日本に上陸。布教許可を求め京を目指しましたが、戦乱で荒廃していたため断念し、代わりに選んだのが山口でした。
整った町並み、住民の高い識字率、そして領主・義隆の寛容さがザビエルの心を動かし、山口はキリスト教布教の拠点となります。こうして山口は東アジア文化と西洋文化が交わる先進的都市となりました。
官職の列が示す朝廷からの信頼
義隆は中央政界との結びつきも深く、任じられた官職は次の通りです。
- 左京大夫
- 筑前守
- 太宰大弐
- 兵部卿(源頼朝も就任した名誉職)
- 伊予介
- 侍従 など
特筆すべきは兵部卿で、武家にとっては最高位に近い名誉職。当時は自称官職が横行していましたが、義隆の官職はすべて実任であり、朝廷からの信頼の高さを物語っています。
大内義隆の最期と後世の評価
しかし、戦国の世は文化力だけでは生き残れませんでした。
軍事から距離を置いた義隆に不満を抱いた重臣・陶晴賢が謀反を起こし、天文20年(1551)義隆は大寧寺で自害。大内氏は急速に衰退し、やがて毛利元就に取って代わられます。
それでも義隆が築いた山口文化は、今川義元・氏真の駿河文化、朝倉義景の越前文化と並び「戦国三大文化」と称されています。軍事面では毛利に及ばなかったかもしれませんが、文化によって人々を豊かにし、異文化を受け入れた政治姿勢は高く評価されています。
戦国時代はどうしても戦の勝敗で評価されがちです。しかし義隆のように、平和的な繁栄を築いた大名もまた、時代を彩る重要な存在でした。
「戦に弱かった」という一面だけでは見えてこない、文化を通して地域を発展させた義隆の真価に、今こそ目を向けるべきではないでしょうか?


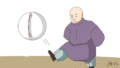
コメント