戦国の乱世を終わらせ、天下を手にした豊臣秀吉。
しかし、豊臣政権は、秀吉の死からわずか数年で徳川家康にとって代わり江戸幕府が開かれることになります。
なぜ、栄華を誇った豊臣政権は、これほどあっけなく終焉を迎えたのか?
そこには、後継者問題・政権構造の限界・家臣団の分裂──さまざまな「不安定さ」が重なり合っていました。
今回は関ヶ原の戦いへとつながる豊臣政権の“終わりの始まり”を、歴史好きの視点からじっくりと読み解いてみたいと思います。
豊臣政権を支えた“影の功労者”──豊臣秀長の死
豊臣政権が短命に終わった理由の一つとして、秀吉の弟・豊臣秀長の早すぎる死を挙げる声もあります。
秀吉が農民から関白という異例の出世を成し遂げた背景には、間違いなく秀長の存在がありました。
軍事・政治の両面で抜群の手腕を発揮し、何より兄・秀吉にとっては唯一といえる絶対的な信頼を寄せられる存在。
まさに豊臣政権を陰から支えた“もう一人の天下人”だったのです。
秀長は25歳で初陣を飾って以来、浅井・朝倉との戦い、毛利攻め、山崎の戦い、賤ヶ岳、小牧・長久手、そして四国・九州征伐まで、主要な戦いの多くでその名が見られます。
武功だけでなく、家臣や諸大名の信頼も厚く、「困ったことがあれば秀長に頼れ」と言われるほど調整力にも優れていました。その功績から、大和・紀伊・河内・和泉を領し、110万石の大名にまで登りつめ、官位は従二位権大納言。
人々からは「大和大納言」と敬われました。
もしも秀長が、兄と同じく62歳まで生きていたなら──
秀次事件も五大老・五奉行の分裂も、未然に防げた可能性は高いでしょう。
実際に秀吉の死後も秀次が政権の中心として機能していれば、家康のような政権交代のチャンスは生まれなかったかもしれません。
それほどまでに、豊臣政権にとって秀長は欠かせない支柱だったのです。
秀長の不在が秀吉政権の土台を見えないところから脆くしていたと考えると、豊臣家の終焉は秀長の死からすでに始まっていたのかもしれません。
秀次切腹事件に後継者不足問題
豊臣政権の脆さを浮き彫りにした事件として、忘れてはならないのが「豊臣秀次切腹事件」です。
農民出身である秀吉には政権を支える有力な一門や外戚が極めて少いのが致命的な弱点でした。
一時は、実弟の秀長や正室・寧々の実家である浅野家の浅野長政が政権の中核を担っていましたが、秀長の死、そして淀殿(茶々)との間に生まれた秀頼の誕生をきっかけに、浅野家との関係も徐々に遠のいていきます。
こうした中で、成人して政権を任せられる人物として浮上したのが、甥の豊臣秀次でした。
秀吉は、わが子・鶴松を失った直後、秀次に関白職を譲り、名実ともに後継者とします。
ところが、その2年後、秀吉と淀殿の間に秀頼が誕生。秀吉にとっては念願の実子であり、当然その後継者に据えたいという思いが生まれたはずです。
こうなると、すでに政権の後継者となっていた秀次の立場は極めて微妙なものになります。
秀吉が疑いを抱いたのか、あるいは秀次が先に危機感を募らせたのか、その真相は不明です。しかし結果として秀次は謀反の疑いをかけられ、高野山に追放され切腹。
さらにはその子や側近までも処刑され、秀次の家系は根絶やしにされてしまいます。
この事件は、豊臣政権の後継体制に決定的な空白を生み出しました。政権を支えるべき有力な一門を自ら排除し、残った後継者はまだ2歳の秀頼ただ一人。政権の屋台骨は一気に不安定化します。
近年では秀次の謀反はでっち上げだったとする見解が有力であり、「殺生関白」という異名すらも、後世に作られたイメージ操作だと考えられています。
豊臣秀頼が幼すぎた──後継者としての“弱さ”
秀吉が亡くなった時、後を継いだ豊臣秀頼は、まだ数えで7歳。
当時の戦国武将の世界では「幼い後継ぎ=チャンス」と見なされてしまいます。
つまり「この家、今が攻めどきだな」と思われてしまうのです。
実際、徳川家康は豊臣政権を内側から支えるというよりも「次は自分が…」と考えていました。
しかも秀頼には、信長の嫡男・信忠や家康の子・秀忠のような「若い頃から戦に出て場数を踏んだ経験」もなかったため、カリスマ性や武将としての実績にも乏しかった。
表向きは「太閤の忘れ形見」として守られていましたが、政権の実権を握るにはあまりに弱く、家康のような老獪な武将からすれば、政権の隙として映っていたことでしょう。
官僚政治の行き過ぎが、武断派との対立を招いた
秀吉の晩年に政権の中枢にいたのは、石田三成をはじめとする文治派と呼ばれる官僚派の家臣たちでした。彼らは戦場よりも法や制度で世の中を整えていく「理詰め」の政治を得意としており、近代的な視点で見るとかなり優れた存在でもありました。
しかし──時代はまだ戦国。
戦で名を上げ、領地をもらい、恩賞で家を盛り立てるという「武功至上主義」が根強く残る中で、三成たちの政治は「頭でっかち」「現場を知らない」と反感を買いやすかったのです。
特に加藤清正や福島正則ら武断派と呼ばれる武将たちにとっては、三成のようなタイプは「戦もろくにせず、秀吉の側にいただけで出世した男」にしか見えなかったでしょう。
実際、朝鮮出兵中にこの対立が表面化し、政権内部の亀裂は決定的なものになっていきます。
秀吉のカリスマでどうにか抑え込まれていた争いの芽は、秀吉の死と同時に一気に噴き出すことになったのです。
二頭政治の限界──五大老と五奉行の機能不全
秀吉が晩年に築いた政権体制は、「五大老」と「五奉行」という2つの合議制グループが政務を担うというものでした。
表向きは、徳川家康・前田利家・毛利輝元ら五大老が国の大方針を決め、石田三成・前田玄以ら五奉行が実務を執るという役割分担。
しかし、実際にはこの二頭政治はうまく機能しませんでした。
なぜなら、秀吉という強力なリーダーが亡くなったあと、両者の間に信頼関係も共通のビジョンもなかったからです。
五奉行の中心だった三成は実務には長けていましたが、人望がありませんでした。一方の五大老、特に徳川家康は、周囲に相談するフリをしながら、着実に自分の権力基盤を強めていきました。
「合議」とは名ばかりで、それぞれが勝手に動き出す──
それが豊臣政権後期の実態でした。
政権を支える屋台骨は、見た目よりもずっと脆かったのです。
豊臣政権に“理想の後継者”はいなかった
秀吉は自分の死後も豊臣家が続くようにと、家康ら有力大名たちを政権のメンバーに加えて体制を整えました。
けれど、冷静に見れば、これは理想の後継者がいなかったということの裏返しでもありました。
豊臣秀次はどうか?
当初、関白職を継いだものの、後に謀反の疑いで切腹させられます。
秀吉の実子・秀頼はあまりに幼く、政権を支えるには荷が重い。
では、周囲の大名たちは?
特に徳川家康が「自分が次に出る番だ」と野心むき出しの行動に出ています。
つまり、「豊臣政権を真に引き継いでいく」という意志と能力を併せ持った人物が、どこにもいなかったのです。この時、一番豊臣政権のことを考えていたのは、石田三成だったのかもしれません。
家康のような別の大黒柱が立ち上がってきた時、それを支えようとする流れが自然とできてしまったのも、この「後継者不在の構造」が原因でした。
秀吉が絶頂期にあった時には見えにくかったこの問題が、カリスマの死後、あっという間に政権の屋台骨をぐらつかせていきます。
関ヶ原は“必然”だったのか?
1600年、ついに徳川家康と石田三成の対立が表面化し、関ヶ原の戦いが勃発します。
表向きは「三成が挙兵し、家康を討とうとした」という構図ですが、ここまでの流れを見れば、これはもはや避けられない戦いだったといえるでしょう。ちなみにこの争いは天下分け目の争いではなく、豊臣政権の権力争いとして位置づけられています。
家康は秀吉の死後すぐに娘を秀頼に嫁がせ、形式的には豊臣家に従う姿勢を見せつつ、その裏で諸大名との縁戚関係を強め、経済・軍事の両面で着実に力を蓄えていきます。
一方の豊臣政権は幼い秀頼に代わって政権を支える人材を欠き、内部分裂と混乱を深めるばかり。
「いずれ誰かが、この政権を終わらせる」
そう思っていたのは、家康だけではなかったかもしれません。
関ヶ原の勝利で政権の実権を握った家康は、豊臣家を政権の座から引きずり下ろし、徳川の時代を切り開いていきます。
つまり、関ヶ原とは一つの政権交代であり、豊臣政権が抱えていた構造的な欠陥が、表に噴き出した瞬間だったのです。
天下を継ぐ難しさ
豊臣政権は、戦国の混乱を治めた天下統一した政権でありながら、その寿命はあまりにも短いものでした。秀吉のカリスマと軍略によって築かれた体制は秀吉の死とともにバランスを崩し、後継者不在・政権内部の分裂・外交と軍事の迷走を経て、やがて徳川の台頭を許すことになります。
豊臣政権の短命ぶりには残念な印象もありますが、逆にいえばここでの失敗があったからこそ、徳川政権の260年という長期安定が築かれたともいえるでしょう。
歴史に“もしも”はありませんが──
もし秀吉が信長のような実力派の後継者を見出していたら?
もし五大老と五奉行が本当に一枚岩だったら?
あるいは、豊臣の世はもう少しだけ続いていたのかもしれません。
そんな「歴史の分岐点」を想像するのも、歴史の楽しみのひとつですね。
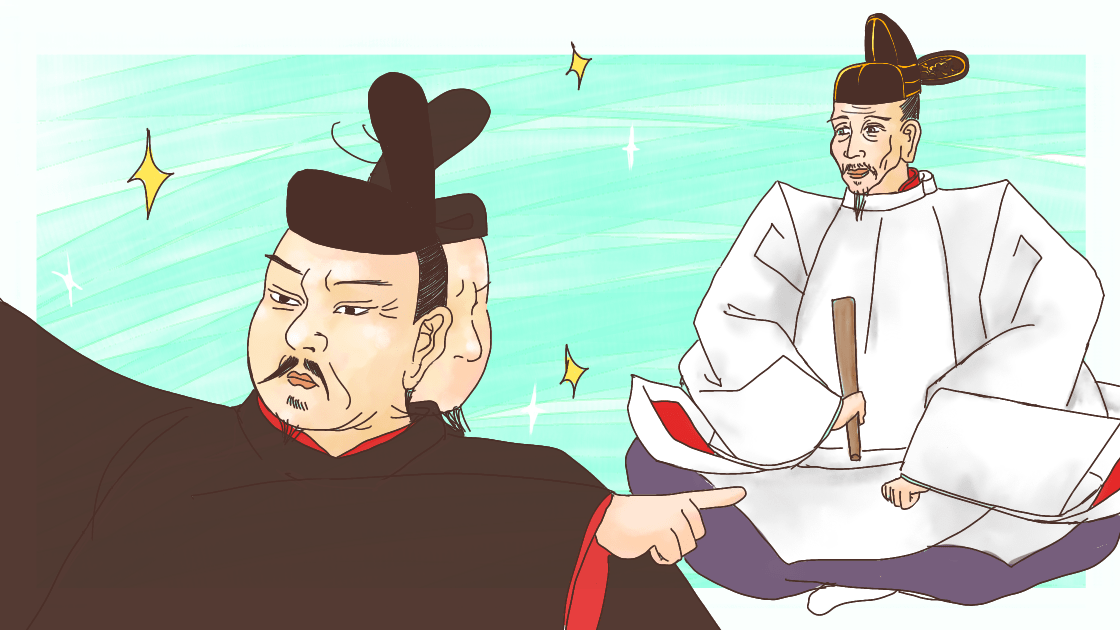

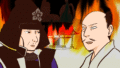
コメント